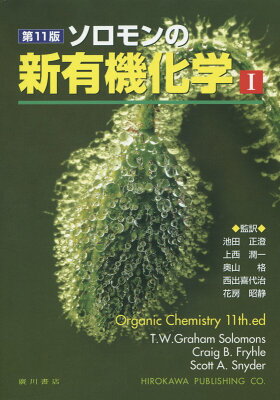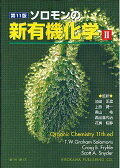【2025年最新版】成績上がる薬学生おすすめの有機化学参考書13選


薬ゼミ模試で化学上位0.1%をとった者です。
(約2万人中23位)
化学は捨てがちな科目ですが、早めに克服しておくと
- 基礎科目の点数が安定する。
- 医療科目に応用が利く。
- 他の科目の問題が化学の知識で解ける。
こういったことに繋がるので化学の勉強を頑張っておくと後がすごく楽です!
そこで今回は、
- 化学の成績を上げたい!
- 講義の内容を理解するための参考書が欲しい
- 講義の知識を国家試験に繋げたい
こんな方のために、僕が実際に読んで良かったものをご紹介します。

僕は、元々化学が苦手でしたが参考書を活用して成績がグンと上がりました。
薬学生におすすめ有機化学の本

買った方が良い順に紹介してるから参考にしてね!
これを買っておけば間違いない!:化学系薬学
薬剤師国家試験を実施している日本薬学会が作っている参考書です。
正直、このシリーズを買っておけば間違いないです。
薬学コアカリキュラム(SBOs)に沿って作られているので、薬学教育に遵守した参考書になっています。
本シリーズは、
- 講義~国試レベルまで幅広く対応。
- 問題がついてるので復習がしやすい。
- 講義の内容を理解するための参考書が欲しい。
こういった特徴があります。

化学系薬学の問題が解ければCBT・国試は大丈夫です!
| 書籍 | 学べること |
| 化学系薬学Ⅰ | ・立体化学 ・基本骨格と反応 ・官能基の性質と反応 ・命名法 詳しい目次はこちら |
| 化学系薬学Ⅱ | ・無機・錯体 ・生体反応を化学で理解する ・医薬品の構造と性質、作用 詳しい目次はこちら |
| 化学系薬学Ⅲ | ・天然物化学化学 ・生薬学 詳しい目次はこちら |
化学系薬学Ⅲは、後述の生薬単と組み合わせて勉強するとより効率的なので2冊併用がオススメです。
生薬を語源から理解できる!:生薬単
日本薬局方第十八改正対応版の最新バージョンです!
個人的には、薬学生必須だと思っています。
この本の利点は、
- B4サイズなので、持ち運びし易い。
- フルカラーで見やすい。
です。

基原植物が写真で載ってるので、理解度UPです。
さらに、生薬それぞれに対して
- 生薬の基原植物名
- 基原植物の実際の写真
- 薬用部位
- 主要成分・構造式
- 漢方処方
が網羅されているので、気になる方は参考にしてみて下さい。
前述の化学系薬学Ⅲと組み合わせると、天然物化学・生薬の準備は万全です!
7,500円するけど充分買う価値アリ!:薬名語源事典
社会人になってから買いましたが、1年生の時から持っておきたかったです。

本屋さんで見た瞬間、感動してAmazonで即買いしました。
突然ですが、インスリン デグルデクの「デグルデクの由来」をご存じでしょうか。
このような内容が載っているのが本書です。
因みにデグルデグの意味は、
ヒトインスリンB鎖30番目のトレオニン残基が欠損(de)し、
グルタミン酸(glutamic acid)を介して
B鎖29位のリジン残基のε-アミノ基が
ヘキサデカン二酸(hexadecanedioic acid)でアシル化されている。
⇒degludec
です。
勿論、インタビューフォームにも同様の記載はありますが名前の由来を気軽に調べられるのが特徴です。

名前の由来なんて覚えて役に立つの?
って思うかもですが、これはメリットが幾つかあります。
実際、インスリンの構造を問う問題が最新の110回で問われています。
ということで医薬品の名前の由来は覚えていた方が得です。

知ってるだけで得する事は多いね!
薬理の授業で一緒に用意したい1冊:化学構造と薬理作用
医薬品は構造から理解した方が確実に記憶に残り易くなります。
例えば、ラモトリギンはバルプロ酸Naと併用注意の薬剤ですが、これをこのまま覚えるよりも「ラモトリギンとバルプロ酸Naは共にグルクロン酸抱合で代謝されるから」と理解して覚えた方が頭に残り易くなります。
実際、109回の実践問題で出題されています。
この問題からも化学と医薬品の重要性が伺えます。
とは言ってもこんな問題を見たら

- こんなのできない。
- 構造出てきたからサヨウナラ。
- 反応なんて暗記じゃん。
と心の叫びが聞こえてきそうですが、化学は基本知識があれば考えれば解くことができるんです。
そう。分からなければ答えを導けば良いんです。
(宗教クサい)
先程の問題はこのように反応が進みます。

この図を見たら暗記でも何でもないですよね。

薬理の全部が化学の知識で解決できるわけじゃないけど、化学で解決できることはとても多いよ!
薬の「性質」を知って理解度UP:薬がわかる構造式集
本書は先程の「化学構造と薬理作用」と比べてライトな内容ですが読みやすいです。
(比較表参照)
| 薬がわかる構造式集 | 化学構造と薬理作用 |
| ・赤シートで官能基・構造のチェックができる。 ・「構造式の覚え方」が載っているので記憶の定着度UP。 | ・収載医薬品数が「薬がわかる構造式集」よりも多い。 ・医薬品を構造から学べるので、薬理学を普通に学ぶよりも圧倒的に理解度が上がる。 |
先程の内容と被ってしまう部分もありますが、近年の国家試験では、
- 構造式の化学的性質を問う問題
- 処方薬の性質を問う問題
- 生物や実務の知識と関連させて解かせる問題
など、より実践的な問題が増えています。
本書はこういった問題を解くために必要な知識がたくさん詰まっているので、化学の実力を付けたい方にはオススメです!
講義の疑問点を解消!:毒の科学
薬は適正な濃度なら病気を治しますが、量が増えると「毒」になります。
- 医薬品
- 農薬
- 麻薬
- 大麻
- 自然毒
など、あらゆる「毒」について学べる1冊です。
カバーしている範囲が広いので講義での疑問点を調べるのに向いています。

フルカラーなのでオススメ!
B4サイズなので講義にも持っていきやすい!
「化学は無意味でしょ」って思ってる人ほど読んで欲しい:くすりのかたち
- 医薬品の性質
- 薬理作用
- 副作用
- ADME
などを化学の観点から説明してる本で、前述の「化学構造と薬理作用」と比べて現場視点での内容が多い為より実践問題向けの内容と言えます。
本書は実践問題の準備としても有効なのでぜひ読んでみて下さい。
一例として、本書中に「ケトプロフェンで光線過敏症が起こる理由」が書かれていますが、実際にこの内容が国家試験でも出題されているので本書を一読する価値は十分にあります。

光線過敏症については僕もまとめた記事があるので良ければご覧ください。
カラーで圧倒的な見やすさ!:ソロモンの有機化学
この本の良いところは、
- 反応する部分や電子の矢印がカラーで見やすい
- 反応機構の過程が抜け目なく書かれている
です。
他の参考書では省かれている反応の過程も本書では丁寧に書かれているので、反応の理解にすごく役立ちます。

反応機構の矢印とかNMRがカラーで解説されてる本は中々ない!
完全に趣味の世界:日本の医薬品構造式集
趣味なら勧めるなよ!
って言われそうですが、構造式って眺めてるだけでも発見があるものです。
- NSAIDsってなんとなくアラキドン酸に構造似てる
- 交感神経作動薬ってほぼ構造一緒じゃん!
- ”ベンズブロマロン”と”アミオダロン”って構造似てない?
他にもいろんな気づきがありますよ!
こうした発見は問題を解く手助けをしてくれることもあるので、なんとなく構造式を眺めてみるというのも面白いと思います。
化学に関する質問
有機化学が苦手です。何から始めればいいですか?

問題を解いて、自分ができない所を明確にしましょう。
何から始めるかを考える前に、何ができないかを明確にしてから勉強をした方が効率的なのでまずは問題を解いてみましょう。
例えば、構造式の問題が出てきて
- 官能基は分かるけどその性質が分からないのか
- そもそも官能基の名前が分からないのか
など、自分がどの程度分からないのかまでしっかり把握することが大切です。
自分の苦手が把握できたら、参考書などを使って理解しけばOKです!
と言っても、化学は理解するのに時間がかかるため友人や先生に聞きながらやっていくのもオススメです。
化学を学ぶ意味ってありますか?

意味はあります!
ざっくり、有機化学をメリットをまとめます。
- 身体の中で起きている反応が理解できる
- 薬理作用・副作用の理解に繋がる
- 新薬の理解に繋がる
化学は勉強は大変ですが、
国家試験の時に大きなアドバンテージになる
現場で薬を調べる時にめちゃくちゃ役に立つ
ので少し苦労しててでも化学は頑張っておいた方がいいです!

まとめ:化学の点数をあげてもっと勉強を楽にしよう!
化学は苦手な人は非常に多い科目ですが、あらゆる分野と繋がっている分野なので早の克服をオススメします!
今回紹介した13冊が参考になれば幸いです。